自己肯定感を高めたいんだけど、うまくいかないな。今日も子どもに怒っちゃったし、もっと自己肯定感が高かったらな・・・


自己肯定感を高めるのって、とても難しいよね。
皆さんは、自分や子どもの自己肯定感を高めたいと思ったことはありますか?
2016年、『自己肯定感を高める教育』についての提言を、文部科学省が取り上げました。この頃から「自己肯定感を高める本」を、書店で多く拝見するようになったと感じます。「自己肯定感」という言葉は、今は広く浸透してきています。
精神科患者さんの中でも、「自己肯定感が低い」ことに悩まれる方は多いです。私は、(自己肯定感を高める行動を試しても変わらない)と悩む方のケアにも携わってきました。
どうやったら本当に「自己肯定感を高める」ことができるのか?
考え続け、だどり着いた答えを今回は共有します。
自己肯定感とは?
▶️自己肯定感とは、「ありのままの自分に価値があると確信していること」です。
「〇〇だから」という条件つきではなく、そのままの自分を受け入れられている状態を指します。
自己効力感との違い
自己肯定感と似ている言葉で、「自己効力感」があります。
▶️自己効力感とは、「自分ならできると自分の能力を信じること」です。
自己効力感は、目標達成に向かって挑戦するときに必要な力となります。過去の成功体験や、他者からの励ましが自己効力感を育むと言われています。
自己肯定感は高めるものではない
自分の存在に価値があるかどうかは、普段の生活で意識することは少ないでしょう。多くの人は、自己肯定感は意識することなく、揺るがずに持っている感覚です。
つまり、自己肯定感そのものには、本来は「高い」も「低い」もないのです。
自己肯定感が高い自分を目指す時点で、自己肯定ができていない状態と言えます。

自己肯定感を求める理由
例えば、失敗をして怒られた時。恋人に振られた時。多くは、「自己否定をする出来事があったとき」に、自己肯定感の高さを求めます。
(ありのままの自分ではいけない)と感じた経験のない人は、いないでしょう。しかし、「自己肯定感が低い人」は、そこで自己否定をする回数が多い、もしくは時間が長いのです。
言わずもがな、自己否定をするために生まれてきた人はいません。そこには、原因や背景が必ずあります。「自己否定」に着目して原因を知ることが、自己肯定感を重要なのです。
自己否定とは?
▶️言葉通り「自分を否定すること」です。
この「自分」には、①能力と②存在の2つの意味が含まれています。
①自己(能力)否定
自己(能力)否定は、失敗したときに起こりやすいです。
失敗に自分の能力は関係しますが、自分の存在価値は関係しません。自己肯定感が下がったと勘違いしやすいですが、本当は自己効力感が下がった状況といえます。
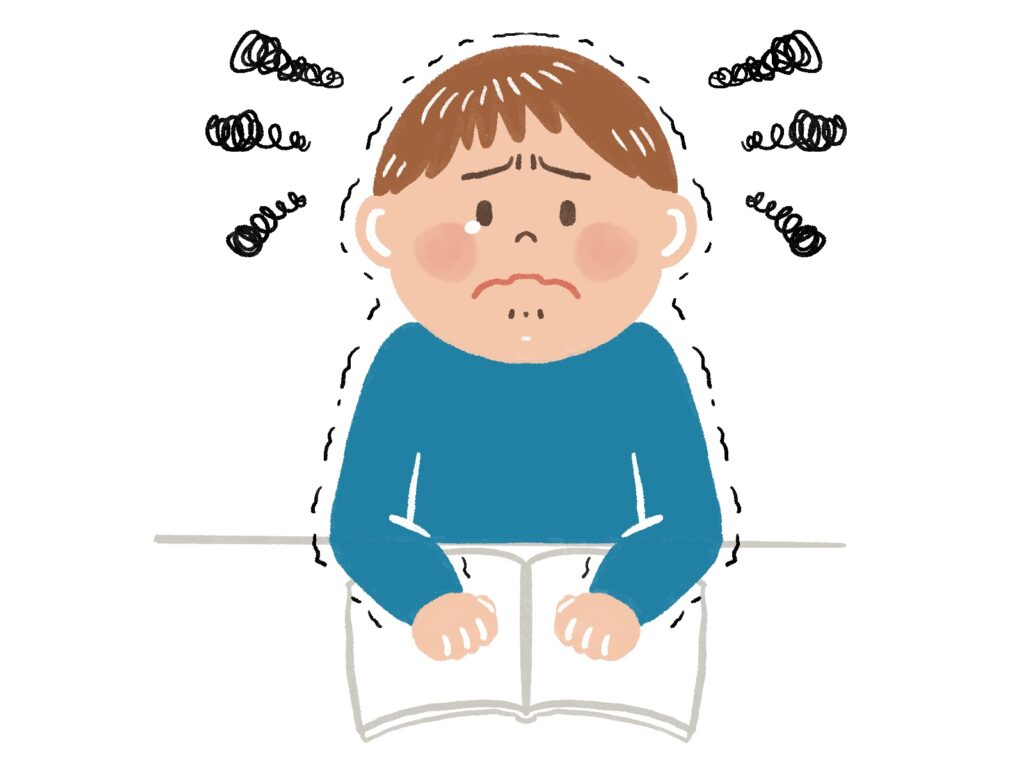
意外と根深い自己(能力)否定

子どもの頃、まわりから否定された経験のない方はいらっしゃいますか?
おそらく、ほぼいないでしょう。
残念ながら、この”まわり”とは親が大部分を占めているのが現実です。また、加熱する受験戦争や学歴重視の世の中、学校教育のあり方も、子どもの自己否定を加速させていると言えます。
否定された経験の多さと成功体験の少なさは、自己効力感を低下させます。そして、「自分の能力」と「自分の存在価値」を混同させた結果、自己肯定感を狂わせるのです。
自己(能力)否定の弊害
否定してきた人(親)から認められるため、その人の評価基準で頑張るようになります。
それが日常となると、「ありのままの自分」とかけ離れた「他者の理想」が目標となります。徐々に、「自分の価値=能力」となり、「ありのままの自分」の存在に価値を見出せなくなります。
その結果、他者の評価や失敗に、自己肯定感が左右されるようになるのです。

自己(能力)否定をなくすには
①失敗をしても、「自分の存在」は無傷です。一つの分野で苦手なことや、できないことがあったに過ぎません。まずは、「自分の存在」と「自分の能力」を分けて考える習慣を身につけ、失敗の捉え方を変えていく必要があります。
②前述したように、(ありのままでいられない)と思うことは誰しもあります。その時に、他者が求める理想なのか?自分の軸で決めた目標なのか?考えてみてください。自分にとって必要な能力であるならば、成長する勇気を出しましょう。
③(どうせ自分はやってもできない、無能な人間だ)と感じていたのは過去です。スモールステップで良いので成功体験を積み、自己効力感を高めることを意識してみましょう。

②自己(存在)否定
多くの場合、否定の仕方と受け止め方が原因で、自己(能力)否定が自己(存在)否定に繋がっています。また、否定してきた人も悪意はなかったり、存在自体を否定しているつもりはなかったりする場合も多いです。
一方で、虐待やいじめ、DV、パワハラなど、存在自体を強く否定されている状況もあります。このような場合では、自己(存在)否定をし、自己肯定感を失っていきます。
自己(存在)否定を抜け出すには
被害の深さが計り知れませんが、その環境から抜け出すこと、周囲に助けを求めることが最も大切です。まずは安全な環境に身を置いた上で、以下の理解を深めていきましょう。
①攻撃的で支配的な人の多くは、その人自身が特性や能力の問題を抱えています。相手を否定している自覚や、傷つけている感覚が持てない場合もあります。ただ、他者を攻撃することで自分の存在価値を示したい、他者の評価基準で生きている人であることは事実です。
②そして、自分を否定してきた人が、この世の全ての人ではありません。自分の周りに「たまたま」居合わせたに過ぎません。居合わせてしまったことは「不運」ですが、これからの人生、ずっと「不幸」が続くわけではありません。
③自分を肯定してくれる他者を求め続けても、今度はその人に「依存」します。自分を肯定できるのは、自分だけです。
④自分の存在価値は、他者が評価するものではありません。「自分らしさを取り戻せ」とは簡単に言えませんが、あなたはあなただけの価値が100%あります。
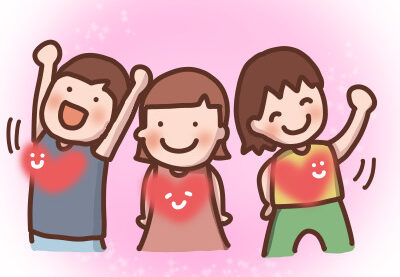
子どもの自己肯定感をどう高めるか
残酷ではありますが、「自己肯定感は親が与える」と言っても過言ではありません。子どもは親に無償の愛を捧げ、親から愛されることを渇望しています。
人は、成長とともに「ありのまま」ではいられなくなります。その時に、「ありのままの自分」を親から認めてもらっている安心感があれば、ありのままの自分を変えていく「成長」に進めます。
親は子どもよりも人生経験が長い分、子どもの変化の先が見えるでしょう。それは「親の理想」であり、「子どものより良い未来」です。しかし、子どもにはまだ見えていない世界がたくさんあります。その中で、遠回りや迂回をしながらも、子どもは子ども自身の力で人生を切り開いていきます。
親が先回りせず、子どもと同じ歩幅で子どもの成長を感じることこそ、子どもの「ありのまま」を認めることであり、子どもの自己肯定感を育むのです。
まとめ
自己肯定感を高めるのではなく、「自己否定」をなくしていく努力をしましょう。
まずは、自分の能力と存在を分けて考え、失敗の捉え方を変えていくと良いです。そして、小さな成功体験から自己効力感を高めていきましょう。
自己肯定感は親の与える影響が大きいため、子どもと同じ歩幅で子どもの成長を見守り、ありのままを認めてあげることが重要です。






