子どもを産んでから、自分に余裕がなくなった気がするなぁ。前はこんなことでイライラしなかったはずなのに・・・


わかるよ〜。子育てしていると余裕がなくなって、その「自分の余裕のなさ」が、子どもに直結してしまうよね。
きつねちゃんと同じお悩みを抱えている、お母さんお父さん。ブログを見にきてくださって、ありがとうございます。
より良い子育てに直結する「親の余裕」をどう作っていくか書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ子育ては余裕がなくなりやすいのか?
子育ては、朝から晩まで(なんなら就寝中まで)毎日毎分毎秒、連続して続く「仕事」です。
子どもが一人で遊んでくれなければ、家事する時間もスマホで連絡を見る時間もありません。子どもが寝なければ、親の自由な時間も睡眠時間も削られます。仕事と違って親(労働者)を守ってくれる法律はなく、代わりの協力者を自ら当てがわない限り「休憩時間」は存在しません。転職や退職もできません。
また、子どもの成長とともに親の悩みは変化します。誰しも子育ては未経験な上、仕事のように「必要なスキル」が定まっているわけではありません。子どもの性格や時期に合わせた臨機応変な対応が、毎回瞬時に要求されます。その対応が正しかったのか一時的な答え合わせをしつつ、評価が返ってくるのは遠い未来の忘れた頃でしょう。
そして、大切な我が子を体を張って守れるのは親だけです。子どもの将来を案じて(こうなってほしい)と使命感や義務感、危機感を感じられるのも、親だけです。だから(この状況をなんとかしなければ!)と思い込むのは当然のことです。知らないおじさんから舌打ちされて、思い詰めるのも当然です。
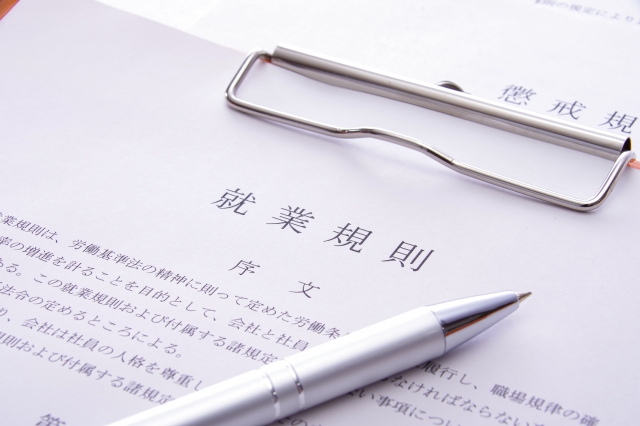
「それらを承知で、覚悟の上で産んだんでしょう?」と言うならば

「想像」と「実践」は全く別物だよ!
と、そちらの想像力の欠如を指摘したくなります。
余裕とは何か
そもそも「余裕」とは何か?
余裕は、①金銭、②時間、③体(健康)、④能力(仕事)、⑤人間関係で構成され、これらが満たされているときに「心の余裕(=メンタルの安定)」が生まれると私は考えています。
人によって、また状況によっても、構成の幅は変わるでしょう。例えば、突発的に友人へ1万円支出しなければならなかったとします。金銭に重きを置いている人は余裕がなくなり、人間関係に重きを置いている人は余裕が生まれるかもしれません。産後で時間や体に余裕がなければ、1万円の出費でも心の余裕がなくなるかもしれません。

余裕を生むために大切なポイント
どの構成も、自分で「どうにかできる部分」と「できない部分」を併せ持っています。どうにかできる部分は、努力で余裕の幅(土台)を広げ、できない部分は「気にしない」マインドと、他に頼ることが必要です。
大切なのは、綺麗な五角形を目指すことが、必ずしも「心の余裕」に繋がるわけではないということです。バランスボールの上に乗っている感覚が伝わりやすいかと思います。

子育て中を「余裕」の構成に当てはめてみる
では、子育て中を、この構成に当てはめてみましょう。
- 【金銭】子どもを育てるにはお金がかかります。子どもが大きくなるにつれ、中学・高校・大学とさらに出費は嵩むでしょう。子どもに「より良い教育」を提供したいなら、学校も塾も習い事もお金が必要となります。よって、余裕はありません。
- 【時間】子どもが生活の中心となります。仕事もプライベートも、誰かの協力がなければその時間を確保することはできません。オンとオフの切り替えも難しいです。余裕はありません。
- 【体(健康)】産後の体はボロボロです。夜泣きがある2歳ごろまでは、睡眠時間が削られます。子どもが走り回るようになれば、こちらが体力を消耗します。そして子どもの風邪をもらい、重症化します。余裕はありません。ボロボロです。
- 【能力】子育てをしていると、自分の未熟さが際立ちます。隣りの子どもを見て、隣の親を見て、自信を無くします。余裕はありません。
- 【人間関係】子どもと新しく「親子関係」を築いていかなければいけません。パートナーとの関係も変化します。自分の両親、義両親、親戚との距離も変わりますが、関係が上手くいくとは限りません。ママ友や先生は「子どもを通して」という新しい関係性で、距離感が難しいです。今までの友人とは気軽に会えなくなります。余裕はありません。

結論、余裕ないです。
こんな状況で「きちんと子育てしよう!」とか「心の余裕を持とう!」と目標を立てれば、余計にメンタルをやられるでしょう。
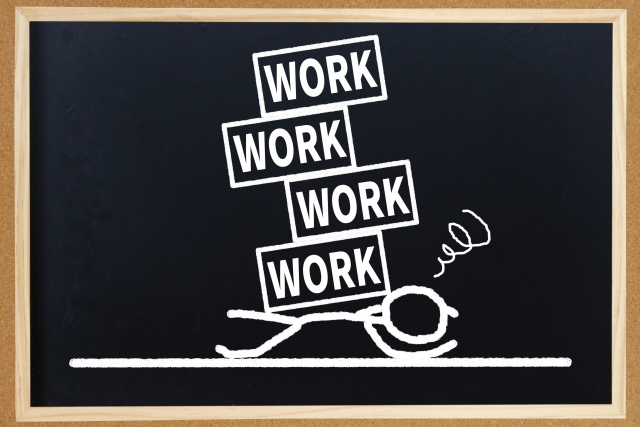
「余裕」を生み出す光はどこにあるのか?
前述した通り、どの分野でも「どうにかできる部分」と「できない部分」があり、人によってその大小は異なります。そもそも子どもを産めば、子どもという他人を優先しなければならず、自分の余裕はなくなります。
その上で、唯一子育てで「どうにかできる部分」は【④能力】です。【④能力】こそ、「余裕」を生み出す光となるでしょう。

ここからは余裕を持つために、必要なステップを挙げていきます。
Step.1 固定概念を変える
子育ては学ぶもの
子どもを産めば、自然と子育てはできるものでしょうか?母性と父性の感覚は、自然と芽生えるものでしょうか?

そんなわけないだろ(=そんなわけありません)。
核家族で少子化で、赤子なんて抱っこしたことない大人がほとんどでしょう。子育ての実態を教えてくれる人だっていません。社会という「理性」の中で生活していれば、「本能」だって薄れていきます。氷河期に生まれ育った20〜40代は、家庭内も「社会」に近く、「本能」を抑制されたまま大人になった方も多いはずです。
昔と今の時代は異なります。「子育ては自然とできるもの」という固定概念は、変えていく必要があるのです。子育てが上手くいかないのは、この時代に親になったから当然のことです。恥ずかしいことでも劣等感を抱えることでもありません。
子育ては変えられる
子どもと接する仕事をしている保育士でも、教育の研究をしている評論家でも、子育ては誰しもが未経験です。知識の差はありますが、全員同じスタートラインであることは事実です。子どもと接することが上手な人でも、「自分の子どもを育てること」はまた別問題です。
また、自分が子どもだった経験はありますが、親になるのは全員初めてです。自分の親から受けた子育ては、子育てのロールモデルとなるでしょう。親との関係性は多少なりとも子どもとの関係性に影響は与えますが、その立ち位置は異なります。そして、そのロールモデルに違和感がある場合は、大人になった今は新しく学んだり修正したりもできるのです。
つまり、子育てがうまくいかない理由に「過去の出来事」を持ち出す必要はありません。「これからどうするか?」と未来の変化を意識すれば、必ず成長できる部分が見えてきます。

Step.2 「良い子育て」から解放される
育児本やSNSは参考程度に
世の中に溢れている育児本には、「より良い子育て」のテンプレが書かれています。そのテンプレを日々どう模範するか、まず第一関門となるでしょう。そして、一般的に「より良い子育て」とは、「今」や「一歩先の未来」ではなく、「未来」で大きな効果が出てきます。余裕がない「今」、「理想の状態」を求めて、手っ取り早く効果の出る方法を選択することは当たり前です。「より良い子育て」は、目の前の問題(現実)と大きな差があるのです。
近年では、育児本からだけではなく、YouTubeやSNSでも「より良い子育て」を学べるようになりました。育児本から「切り抜いた一点」を活かすより、身近に受け取れるようになったメリットはあります。一方で、YouTubeやSNSも「切り抜かれた一部」という認識が低下し、現実との比較に繋がるようになりました。
このように「より良い子育て」が浸透してきている今、手っ取り早く効果の出る「あまりよろしくない教育」には、罪悪感や劣等感を抱きやすくなっています。
そのことを理解し、育児本やSNSとの距離感を学んでいく必要があります。
隣の芝生は青く見える
子どもはモノではないと分かりつつ、隣の子どもがよく見えた経験はありませんか?
順位が明確になる勉強や運動が始まれば、子どもの得意不得意も足りない部分も必ず目につきます。子どもの将来がより良いものであることを、願っていない親はいません。口や態度に出さないだけで、どの親も子どもの順位を気にして「比較」しています。子どもを育てる上で、「比較」をしてしまうことは仕方がないと思ってください。
その上で、その「比較」した部分は、子どもの人生の「一点」に過ぎません。子どもの成長は千差万別で、大器晩成の子どももいます。「今」できていることは素晴らしいですが、早熟な可能性もあるのです。
「良い子ども」を求めた「良い教育」は五万とあります。しかし、そこを追求することが「幸せ」かは分かりません。「良い教育」は大切ですが、「良い子ども」を親は求めてはいけないのです。

Step.3 子どもと上手に距離を取る
「子育て四訓」を意識する
- 乳児はしっかり肌を離すな
- 幼児は肌を離せ、手を離すな
- 少年は手を離せ、目を離すな
- 青年は目を離せ、心を離すな
これは、子どもの成長に合わせて親の接し方を学ぶ言葉です。
放置や無関心でも過干渉でもなく、「適切な距離で子どもと接すること」が最も重要な親の在り方なのです。余裕がなく追い詰められている時は、子どもとの距離感を意識して変えてみてください。
「まあ、いっか」と思えるのも能力
子どもは他人です。親ができることは、子どもを導くまでです。その後の選択は、子ども次第となります。そして、親も子どもも完璧ではありません。そのことを忘れず「まぁいっか」と許容できることも、子育てには必要な能力なのです。

Step.4 子どもの成長=自分の成長
子どもの「できた!」は、私が「できた」から
子育てに自信のない方は、大勢いらっしゃいます。

でも、本当に子育てできていないですか?
子どもは、毎日成長します。その成長を支えているのは、親です。親がきちんと子育てをできているから、子どもは成長できるのです。
子どもの小さな「できた!」でも、親も自分の仕事が「できた」と自信をもってください。
子育てから「己育て」へ
子育ては、仕事のように決まっている「能力」はありません。その代わりに「自分が成熟していること」が必要となります。自分を見つめ直し、自分の内側を変化させていくことは、どの仕事よりも高度と言えるでしょう。
親が自分自身を育てる努力は、結果として「心の余裕」を生み出すことになります。子育て以上に、「親育て」を意識して生活してみてくださいね。







